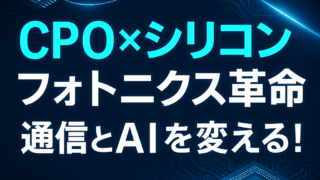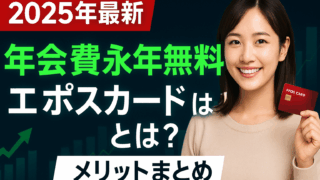「株式投資に興味があるけど、リスクが怖くて踏み出せない…」
「老後のために資産形成を始めたいけど、何から手をつければいいのかわからない…」
「投資は難しそう…初心者でも本当に始められるの?」
このような悩みをお持ちではありませんか?
結論から言うと、株式投資は正しい知識と戦略があれば、初心者でも十分に始められる資産形成の手段です。実際、日本では約2,400万人が株式投資を行っており、銀行預金よりも高いリターンを得るための選択肢として年々注目度が高まっています。
この記事では、株式投資の基本的なメリット・デメリットから具体的なリスク管理方法、初心者でも安心して始められる投資戦略まで徹底解説します。記事の最後まで読めば、あなたも自信を持って株式投資の第一歩を踏み出せるでしょう。

株式投資の基本:そもそも株とは何か?
株式投資について理解する前に、まずは「株」とは何かをシンプルに解説します。
株式(株)とは、企業の所有権の一部を表す証券です。つまり、ある企業の株を購入すると、その企業のオーナーの一人になるということです。あなたが1000株を保有し、会社の発行株式総数が100万株だとすると、あなたはその会社の0.1%を所有していることになります。
株主になると主に3つの権利を得ることができます:
- 議決権:会社の重要な決定に対して投票する権利
- 配当受領権:会社の利益の一部を受け取る権利
- 株式売買権:保有する株式を自由に売買する権利
株価が上昇すれば購入時よりも高い価格で売却できるため利益(キャピタルゲイン)が得られ、企業が利益の一部を株主に分配すれば配当金(インカムゲイン)も得られます。この二つが株式投資の主な収益源です。
株式投資のメリット:なぜ株式投資が資産形成に効果的なのか
株式投資には多くのメリットがあり、だからこそ多くの人が資産形成の手段として選んでいます。主なメリットを見ていきましょう。
1. 長期的に高いリターンが期待できる
日本の株式市場(日経平均株価)は長期的に見ると年率約5〜7%のリターンを生み出してきました。これは銀行預金の金利(0.002%程度)と比較すると圧倒的に高い数字です。
例えば、毎月3万円を30年間投資した場合:
- 銀行預金(金利0.002%):約1,080万円
- 株式投資(年利5%と仮定):約2,520万円
長期投資の力で資産を大きく増やせる可能性があるのです。
2. インフレから資産を守ることができる
物価上昇(インフレ)は預金の価値を実質的に目減りさせますが、株式は企業の成長とともに価値が上昇するため、インフレに対する防衛策となります。企業は物価が上がれば製品価格も上げることができるため、株価もそれに応じて上昇する傾向があります。
3. 少額から始められる
現在は1株から購入できる銘柄も多く、1000円程度から投資を始めることも可能です。また、投資信託を活用すれば100円から分散投資ができます。資金が少なくても始められるのは大きなメリットです。
4. 配当金という副収入が得られる
多くの企業は利益の一部を株主に還元するために配当金を支払います。配当利回りの高い銘柄を選べば、株価の上昇に加えて定期的な収入も期待できます。日本企業の中には配当利回りが3〜4%に達する企業もあります。
5. 税制優遇が受けられる
NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を活用すれば、通常20.315%かかる税金が非課税または控除の対象となります。特に2024年から始まった新NISA制度では、年間最大360万円までの投資が非課税となり、より効率的な資産形成が可能になりました。
株初心者から上級者まで、幅広く選ばれているDMM 株(PR)
![]()
株式投資のデメリット:リスクを正しく理解する
メリットがある一方で、株式投資には必ずリスクが伴います。初心者が挫折する原因の多くは、これらのリスクを正しく理解せずに投資を始めてしまうことにあります。
1. 元本保証がない
銀行預金と異なり、株式投資には元本保証がありません。株価は上下するため、購入時よりも価格が下落した状態で売却すると損失が確定します。景気後退時には市場全体が大きく下落することもあります。例えば、2008年の金融危機では日経平均株価が約50%下落しました。
2. 短期的な価格変動がある
株価は日々変動するため、短期的には大きく上下します。この変動に一喜一憂すると、冷静な判断ができなくなる可能性があります。特に、個別銘柄は予想外のニュースで一日に10%以上価格が変動することも珍しくありません。
3. 情報収集と分析が必要
効果的な投資を行うためには、企業や経済の基本的な知識、情報収集能力が求められます。時間と労力をかけて学び続ける必要があり、これが負担に感じる人もいます。
4. 感情に振り回されるリスク
株価が下がると不安になり売却してしまう、上がり続けると欲が出て買い増してしまうなど、感情に左右されて非合理的な判断をしがちです。実際、多くの個人投資家は「高値で買い、安値で売る」という最悪のタイミングで取引してしまう傾向があります。
5. 流動性リスク
時に株を売りたいと思っても、買い手がいない(特に小型株の場合)というリスクがあります。また、急に資金が必要になった時に、株価が下がっている局面だと損失確定を余儀なくされることも。

初心者でも安心!リスクを抑えた株式投資の始め方
デメリットを見ると不安になるかもしれませんが、適切な戦略を持てば初心者でもリスクを最小限に抑えながら投資を始めることができます。まずは基本的な考え方から見ていきましょう。
長期投資の重要性:時間があなたの最大の味方
株式投資で最も重要なのは「長期的な視点」です。短期的な株価変動に一喜一憂せず、5年、10年、20年という長い時間軸で投資することで、リスクを大きく軽減できます。
例えば日経平均株価の過去データを分析すると、投資期間が長くなるほど損失を出す確率は低下します:
- 1年間の投資:約35%の確率で損失
- 5年間の投資:約15%の確率で損失
- 10年間の投資:約5%の確率で損失
- 20年間の投資:ほぼ0%の確率で損失
短期的な相場予測は専門家でも難しいものですが、長期的には経済成長とともに株価は上昇する傾向があります。「時間の分散」こそが、初心者にとって最も効果的なリスク管理法なのです。
分散投資の基本:すべての卵を一つのカゴに盛るな
次に重要なのは「分散投資」です。1つの銘柄や1つの業種だけに集中投資すると、その銘柄や業種が不調になった時に大きな損失を被るリスクがあります。
効果的な分散投資の方法は以下の通りです:
- 銘柄の分散:複数の企業に投資する
- 業種の分散:IT、金融、医療、消費財など様々な業種に投資する
- 地域の分散:日本株だけでなく、米国や新興国など異なる地域にも投資する
- 資産クラスの分散:株式だけでなく、債券や不動産など異なる資産クラスにも投資する
- 時間の分散:一度にまとめて投資せず、定期的に分けて投資する(ドルコスト平均法)
初心者にとって最も手軽な分散投資の方法は、インデックス投資信託やETF(上場投資信託)を活用することです。これらの商品は多数の銘柄に自動的に分散投資できるため、個別銘柄選びの難しさを回避できます。
【サクソバンク証券】外国株式口座開設自分に合った投資スタイルを見つける
投資スタイルは人それぞれです。自分の性格や生活スタイル、リスク許容度に合わせた投資法を選ぶことが重要です。
1. 忙しい人・勉強する時間が限られている人向け
毎月一定額をインデックスファンドに積み立てる「ほったらかし投資」が最適です。TOPIXや日経平均、S&P500などに連動するインデックスファンドを選び、長期的に積み立てていく方法です。手間がかからず、長期的に市場平均のリターンが期待できます。
2. ある程度勉強する時間がある人向け
インデックス投資をベースとしつつ、一部を個別株投資に充てる「コアサテライト戦略」が有効です。資産の70〜80%を安定したインデックスファンド(コア)に、残りの20〜30%を自分で選んだ個別株(サテライト)に投資します。この方法なら、市場平均を上回るリターンの可能性を追求しながらも、リスクを抑えられます。
3. 積極的に勉強して高いリターンを狙いたい人向け
投資に時間をかけられる場合は、バリュー投資やグロース投資など、より専門的な投資手法を学ぶのもよいでしょう。ただし、初心者のうちは資産全体の一部(20%程度)だけを使って試すことをおすすめします。

初心者のための具体的な株式投資の始め方:5つのステップ
具体的にどうやって株式投資を始めればよいのか、順を追って説明します。
ステップ1:投資の目的と期間を明確にする
まずは「なぜ投資をするのか」「いつまでにいくら必要なのか」を明確にしましょう。目的と期間によって、適切な投資戦略は変わってきます。
- 短期(1〜3年):結婚資金、車の購入など → 安全性重視の投資
- 中期(3〜10年):住宅頭金、子どもの教育資金など → バランス型の投資
- 長期(10年以上):老後資金、資産形成など → 成長性重視の投資
目標が明確になれば、一時的な株価変動に動揺することなく、長期的な視点を持ち続けられます。
ステップ2:投資に回せる資金を決める
株式投資を始める前に、以下の3つの条件を満たす資金計画を立てましょう:
- 生活防衛資金の確保:突発的な出費に備えて、最低でも生活費の3〜6ヶ月分は現金で持っておく
- 借金(特に高金利のもの)の返済:クレジットカードのリボ払いなど高金利の借金がある場合は、先にそれを返済する
- 無理のない投資額の設定:月々の収入から生活費や固定費を引いた余剰資金の範囲内で投資する
特に初心者は「損しても問題ない資金」だけで投資を始めることが重要です。失って困るお金は決して投資に回さないでください。
ステップ3:証券口座を開設する
株式投資を始めるためには、証券会社で口座を開設する必要があります。初心者におすすめの証券会社の選び方のポイントは以下の通りです:
- 手数料の安さ:取引コストは投資成績に直結します
- 使いやすいアプリ・ウェブサイト:直感的に操作できるインターフェースがあると便利
- 豊富な商品ラインナップ:国内株式だけでなく、投資信託や海外株式なども取り扱っていると選択肢が広がる
- 教育コンテンツの充実度:初心者向けのセミナーや解説記事が充実していると学びやすい
- サポート体制:疑問点があった時にすぐに問い合わせられるサポート体制があると安心
特にDMM 株は、使いやすい取引アプリ、手頃な手数料、充実した投資情報コンテンツを提供しており、初心者にも使いやすいと評判です。
ステップ4:NISA口座も同時に開設する
投資で得た利益には通常20.315%の税金がかかりますが、NISA口座を利用すれば税金がかからないため、効率よく資産を増やすことができます。特に2024年から始まった新NISAは制度が大幅に拡充され、より使いやすくなりました。
新NISA制度の主な特徴:
- 成長投資枠:年間120万円まで投資可能、非課税保有期間は無期限
- つみたて投資枠:年間240万円まで投資可能、非課税保有期間は無期限
- 生涯非課税投資総額:合計1,800万円まで
通常の証券口座と同時にNISA口座も開設しておくことで、税制優遇を最大限に活用できます。まずは「つみたて投資枠」から始めるのがおすすめです。
ステップ5:最初の投資商品を選ぶ
初心者が最初に選ぶべき投資商品は、分散投資が自動的にできるインデックス投資信託やETFです。特につみたてNISAで購入できる商品は、金融庁が定めた基準をクリアした低コストで分散効果の高い商品ばかりです。
初心者におすすめの投資信託の例:
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー):世界中の株式に分散投資
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):米国の主要500社に分散投資
- ニッセイ日経225インデックスファンド:日本の主要225社に分散投資
これらの投資信託は数千円から購入できるため、少額から始められます。毎月一定額を積み立てる「ドルコスト平均法」を活用すれば、相場の上下に関わらず平均的な価格で購入できるため、タイミングを計る必要がありません。

投資で失敗しないための5つの心構え
最後に、株式投資を続けていく上で大切な心構えを解説します。多くの初心者が失敗するのは、技術的な問題ではなく「心理的な問題」によることが多いためです。
1. 焦らない・欲張らない
投資は「急がば回れ」が鉄則です。短期間で大きな利益を得ようとすると、必要以上にリスクを取ってしまいがちです。「塵も積もれば山となる」という気持ちで、コツコツと積み立てていくことが長期的な成功につながります。
2. 他人の成功に惑わされない
SNSやネット上では「株で大儲け」という話があふれていますが、失敗例はあまり公開されません。友人や知人が「○○株で儲かった」と言っても、それに影響されて同じ銘柄に飛びつくのは危険です。自分の投資計画を信じて、ブレないようにしましょう。
3. 相場の予測に頼らない
「今が底値だから買い時」「これから株価は上がる/下がる」という予測は、専門家でさえ当たらないことが多いものです。相場予測に頼るのではなく、定期的に分散投資を続ける戦略を取ることで、良いタイミングも悪いタイミングも平均化できます。
4. 損切りのルールを決めておく
特に個別株に投資する場合は、あらかじめ「いくらまで下がったら売る」という損切りラインを決めておくことが重要です。感情に任せて「もう少し待てば戻るかも」と持ち続けると、取り返しのつかない大きな損失になりかねません。
5. 継続的に学び続ける
投資の世界は常に変化しています。一度身につけた知識で満足せず、新しい情報や考え方を取り入れる柔軟さが必要です。書籍やセミナー、信頼できる投資情報サイトなどを活用して、継続的に学び続けましょう。
信用取引を始めるなら【DMM 株】!(PR)株式投資に関するよくある質問
Q1: 株式投資を始めるのに最低いくら必要ですか?
A: 現在は1株から購入できる銘柄も多く、数千円から始めることが可能です。また、投資信託であれば100円から購入できるものもあります。特に「つみたてNISA」を活用すれば、毎月1,000円からでも効率的な分散投資を始められます。大切なのは金額の大小ではなく、早く始めて複利の効果を最大化することです。
Q2: 株式投資で確実に儲かる方法はありますか?
A: 残念ながら、株式投資で「確実に」儲かる方法はありません。しかし、長期・分散・積立の3原則を守り、低コストのインデックス投資を継続することで、長期的には市場平均のリターンを得られる可能性が高まります。過去のデータを見ると、20年以上の長期投資では、ほとんどのケースでプラスのリターンとなっています。
Q3: 投資を始めるのに良いタイミングはいつですか?
A: 「ベストなタイミング」を待つ必要はありません。実は、株式投資で最も重要なのは「投資期間の長さ」であり、始めるタイミングではないというデータがあります。特に積立投資なら、市場が上がっても下がっても平均的な価格で購入できるため、「今」始めることが最良の選択です。「Time in the market beats timing the market(市場にいる時間は、市場のタイミングを計ることよりも重要)」という言葉は、投資の世界では有名な格言です。
Q4: 株と投資信託、初心者はどちらから始めるべきですか?
A: 多くの専門家は、初心者には投資信託(特にインデックスファンド)から始めることをおすすめしています。理由は主に3つあります。①少額から分散投資できる、②プロが運用してくれるので個別銘柄分析の知識が不要、③定期的な積立設定が可能で感情に左右されにくい。ある程度投資の基礎を学んだ後に、資産の一部で個別株投資にチャレンジするのが理想的です。
Q5: 株価が下がってきたらどうすればいいですか?
A: 株価の下落は投資の過程で必ず起こるものです。長期投資を前提としている場合は、パニックにならず冷静に対応することが大切です。むしろ定期的な積立投資をしている場合は、株価下落時は「より安く買えるチャンス」と捉えることもできます。ただし、個別企業の株価が会社の根本的な問題で下落している場合は、投資判断の見直しが必要かもしれません。このため、特に初心者は分散効果の高いインデックス投資から始めることをおすすめします。

まとめ:今日から始める株式投資の第一歩
株式投資は決して難しいものではなく、正しい知識と戦略があれば、誰でも始められるものです。この記事で紹介した内容をおさらいしましょう。
- 株式投資のメリット:長期的に高いリターンが期待できる、インフレから資産を守れる、少額から始められる、配当金という副収入が得られる、税制優遇が受けられる
- 株式投資のデメリット:元本保証がない、短期的な価格変動がある、情報収集と分析が必要、感情に振り回されるリスク、流動性リスク
- リスクを抑える方法:長期投資の視点を持つ、分散投資を行う、自分に合った投資スタイルを選ぶ
- 始め方の具体的ステップ:投資の目的と期間を明確にする、投資に回せる資金を決める、証券口座を開設する、NISA口座も同時に開設する、最初の投資商品を選ぶ
- 投資の心構え:焦らない・欲張らない、他人の成功に惑わされない、相場の予測に頼らない、損切りのルールを決めておく、継続的に学び続ける
株式投資の真の目的は、一攫千金を狙うことではなく、長期的な視点で着実に資産を増やしていくことです。「急がば回れ」の精神で、コツコツと投資を続けていくことが、将来の経済的自由への鍵となるでしょう。
まずは少額からでも投資を始めることで、実践的な学びを得ることができます。この記事を読んだ今、ぜひ第一歩を踏み出してみてください。あなたの豊かな未来のために、今日からできることから始めましょう。
※投資にはリスクが伴います。投資を行う際は、ご自身の判断と責任においてお願いします。本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄や投資信託、証券会社等の推奨を目的としたものではありません。